著名IT企業役員が、兼業という選択で挑戦するもう1つのフィールドとは
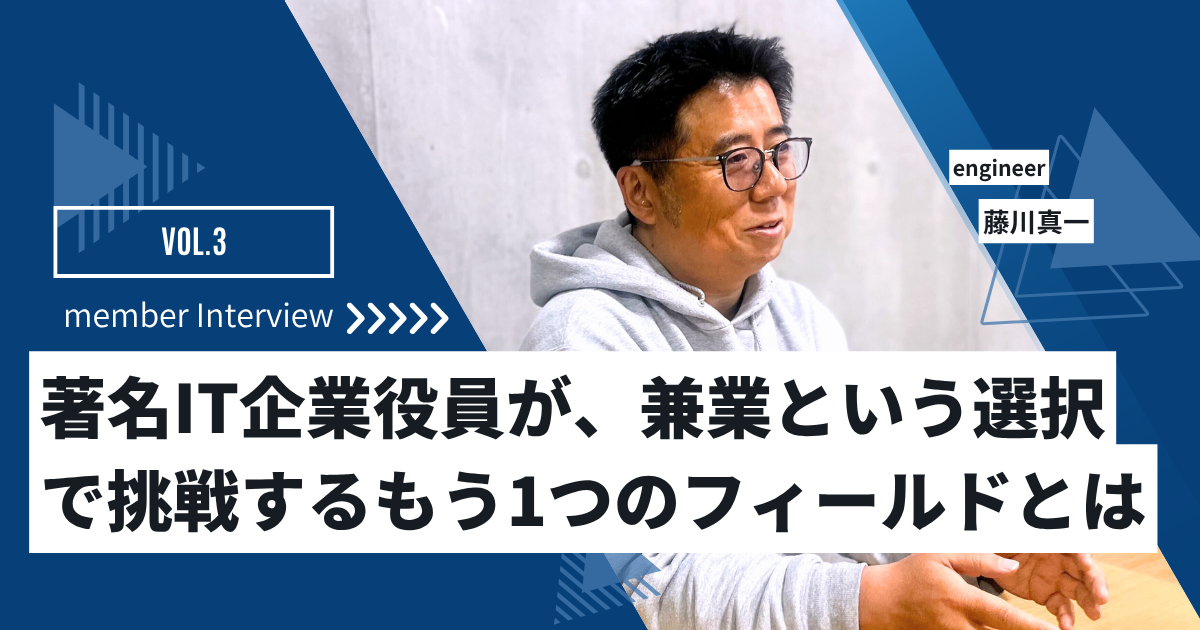
PROFILE
藤川真一 Material Foundation Team
埼玉県出身。FA装置メーカーを経て、2000年にWeb制作ベンチャーに参画。2006年からWebサービス業界に転身し、翌年より携帯向けTwitterクライアント「モバツイ」の開発・運営を手がける。2014年にBASE株式会社 取締役CTOに就任し、2019年から同社 上級執行役員 SVP of DevelopmentおよびPAY株式会社 取締役を歴任。2018年、慶應義塾大学大学院にて博士(メディアデザイン学)を取得。
モバツイ開発を経て。新たな挑戦への決意
ーー現在に至るまで様々な経験をされていますが、どのような道のりだったのでしょうか?
大学では工学部に在籍し、ロボット開発などに取り組んでいた流れで、卒業後は装置メーカーで開発業務を担当していました。その後いわゆる初期のネットバブルの時代がきてインターネットの可能性に惹かれ、デジタルハリウッドで学び直したのち、Web制作ベンチャーへ転職しました。そこでは動画CMSや社員教育向けのLMS開発などに携わり、Webサービスの面白さを実感しました。
2006年にGMOペパボ株式会社(当時paperboy&co.)に転職し、ECサービスの開発・プロダクトオーナーを担当。並行して個人で「モバツイ」というTwitterのガラケー向けサービスを開発・運営し、この事業の成長をきっかけに独立をしました。その後、東日本大震災が起きた頃に、スマートフォンの時代が一気に到来したことをきっかけに、LINEのようなサービスも出てきて、コミュニケーションの在り方がガラッと変わりました。モバツイはガラケー向けサービスだったので、そこにうまく乗り切れなかったんですよね。最終的には会社を譲渡し、また次のチャレンジへと向かっていくことになりました。
ーー会社の譲渡や再チャレンジの背景には、どのようなきっかけや思いがあったのでしょうか?
当時モバツイの今後の方針について悩んでいた中で、取締役として参画していた、現クロステック・マネジメント代表の小笠原に相談する機会がありました。その際に「一度手放して、身軽になって別の事業にもう一度挑戦してみたら?」という助言をもらい、その言葉に背中を押されて、会社を譲渡し再び起業に踏み出す決意を固めました。
その後はスマートフォンアプリの開発に挑戦したのですが、ひとりでの開発が自分に合っていないことに気づき、複数の会社に関わる中で出会ったのがBASE株式会社です。最初は技術顧問として関わっていましたが、資金調達を機に正式に取締役CTOとしてジョインすることになり、2010年8月から本格的に参画しました。その後BASEは上場を果たし、組織の拡大に伴い、採用や社内体制の整備・内部統制など経営面の課題にも多く関わるようになりました。現在はCTOの役割を後任に引き継ぎ、開発組織全体を統括するSVP of Developmentという役割で、引き続き開発チームの成長を支えています。
「教育版GitHub」を目指して。実現のために自分ができること

ーークロステック・マネジメントにジョインされた経緯についてお聞かせください。
現在はBASEで勤務しながら、兼業という形でジョインしています。元々、既に仕組みや体制が整っている会社や学校などのIT化に興味があり、小笠原からクロステック・マネジメントが目指している教育機関のIT化の話を聞いて面白そうだと思いました。芸術大学という側面に、独自の面白さや可能性のようなものを感じたんです。今後この事業が描いている世界観、そして海外展開の可能性まで視野に入れると、非常にポテンシャルがあるなと。その一端を外から見るのではなく、どうせなら中から関わりたい。そう思い「自分にできることがあれば手伝います」と自分から声をかけたんです。
ーークロステック・マネジメントではどのようなことをされているんですか?
大学やクロステック・マネジメントが「実現したい世界観や理念」を、技術的にどう実装していくかの役割を担っています。世界観や理念の言葉には、一つひとつ明確な意図があり、それをただの仕様として受け取るのではなく、その背景にある思想を理解したうえで技術に落とし込むことが求められます。「教育」とひとことで言っても、その中にはいろんな要素が含まれていると思うんです。たとえば、「授業」と「教材」の違いを意識して、設計することが重要となります。
授業は、教員によるライブパフォーマンスや学生とのインタラクションを含む学びの場であり、一方で教材は授業を支える学習用のコンテンツ(例:動画教材、副教材、スライドなど)を指します。授業は教材を活用しながら進行しますが、教員とのやり取りを含む「授業の形態」には固有の特性があり、教材とは明確に区別して捉える必要があります。そこをふわっと受け取ってしまうと、全く違う方向に設計が進んでしまうリスクがあるため、「これはこういう意図ですよね?」と確認を重ねながら、言葉の定義を丁寧に整えていくことがとても重要です。
そのうえで、それらの思想を技術的にどのような形で落とし込むか、仕様にどう反映するかを考える。僕はエンジニア寄りの立場なので、そういった思想や構造を要件定義やプロトタイプへと具体化する部分を主に担っています。
ーー大学やクロステック・マネジメントが「実現したい世界観」とはどんなものですか?
たとえば「Learning Materials Hub」っていう構想があるんですけど、それは教材を"素材"として扱って、再編集や流用ができる世界を目指しているんです。まさに「教育版GitHub」みたいなイメージですね。ただ、それをそのままエンジニア目線で実装してしまうと、先生方にとっては使いづらいものになってしまう可能性があります。議論をせずに開発を進めてしまうことで、エンジニア特化型のパーツを作ってしまい、結局誰にも使われない。そんな状況になりかねません。それは、一番避けたいことだと思っています。だからこそ、「どうすれば現場の先生たちにも届くか?」という視点を常に持ちながら、議論を重ねています。
教材の権利の問題だったり、生成AIの活用、Google ClassroomやNotionとの連携をどうするか、といった具体的な技術課題もあるんですけど、それら一つひとつが最終的に「小笠原が実現したい世界」につながっているかどうかを確認しながら進めています。
仲間とともに。進化するプロジェクトを

ーー実際にプロジェクトに関わってみて、どのように感じていますか?
正直、めちゃくちゃ大変なプロジェクトですよ(笑)。特に大変なのは、大学という組織の根本的な仕組みに踏み込もうとしている点です。それに加えて、将来的にはこの思想を他の設置校にも広げていこうとしている。これってただのシステム開発じゃなくて、価値観そのものをアップデートする試みだと思っています。
その分、非常に大きなやりがいも感じています。だからこそプロジェクトが円滑に進むように、自分にできることは積極的に取り組んでいきたいと考えています。たとえば、VPoEが開発組織のビルディングに苦悩する時や、リードエンジニアがアプローチに迷う時、メンバーが業務を通してエンゲージメントが落ちる時など。マクロからミクロまで対象は広いですが、自分の役割はそんな時にそっと軌道修正することだと思っています。
ーーそうした役割に対する意識は、どのような経験から生まれたのでしょうか?
起業経験やBASEでエンジニア組織のリーダーを務めている経験が大きいです。組織がうまく回らない時って、多くの場合「寂しさ」に原因があると思うんですよね。コミュニケーションのズレや期待の相違が積み重なり、最終的に人が離脱することで組織の歯車が狂うことが多いからです。そのため、どんな環境においてもチームメンバーが働きやすい環境を考え、「寂しい思いをさせない」ことを信条にしています。
ーー小笠原について、今回のプロジェクトで改めて感じたことはありますか?
これまで小笠原とアドバイザー的な立場で一緒に仕事をしたことはありましたが、クロステック・マネジメントのように組織のトップとして構想から現場まで牽引している姿を見るのは初めてで、とても刺激を受けています。
たとえば週次の全体会議や定期開催のキックオフで小笠原が伝えている「失敗に対する向き合い方」や「自分の考えをどう形にしていくか」といった考え方にすごく学びがありました。マネジメントスタイルにしても、人に期待し続け、たとえ過去に裏切られた経験があっても、チームメンバーに期待し、信じて役割を託していくその姿勢から多くを学んでいます。
さらにこのプロジェクトには、過去にどこかで出会った人たちが多く関わっていて、個人的にも驚きや嬉しさがあります。それも小笠原がこれまで築いてきた信頼や人脈の証だと思っています。これだけ多くの人が「また一緒にやろう」と集まってくる。その関係性の構築力は本当にすごいと思います。もちろん、今のプロジェクト規模も背景にありますが、それを活かしながら多様なメンバーを巻き込み、噛み合わせていく力は、まさに小笠原だからこそ実現できていることだと感じます。スタートアップをゼロから立ち上げるというよりも、これまでの経験や出会いを“集大成”として形にしようとしているような場で、自分がその一部になれていることを非常にうれしく思います。