“自分でつくる”キャリア──ファッションデザイナー志望だった僕がVPoPになるまで
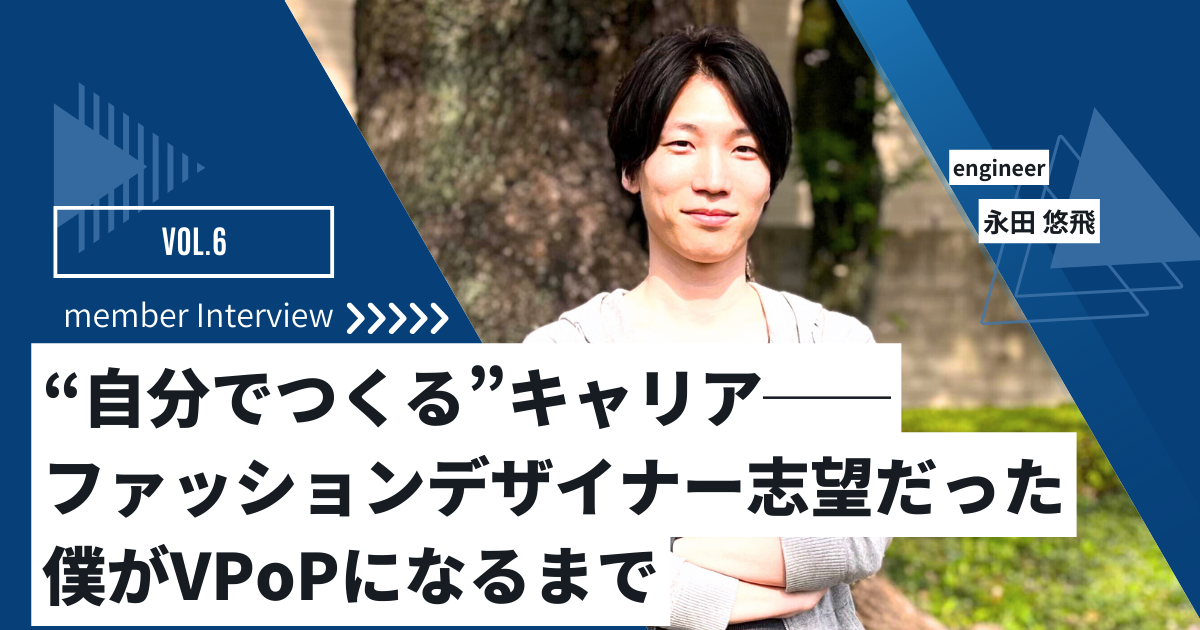
PROFILE
永田 悠飛 Dev Ops Dept. VPoP
ファッションデザイン専門学校卒業後、アパレル業界で約6年間、販売・営業、商品企画に従事。2019年に退職し、半年間プログラミングを学習。同年にソフトウェアエンジニアとして独立し、株式会社tsumugに参画。フロントエンドエンジニア兼スクラムマスターを担当。2022年にソフトピース株式会社を設立。2023年より株式会社クロステック・マネジメントに専任スクラムマスターとして参画し、現在は同社のVPoP(Vice President of Process)として開発組織のマネジメントを担う。
ものづくりの先に辿り着いた、エンジニアという選択肢

──現在に至るまで、どのようなキャリアを歩まれてきたのでしょうか?
元々“ものづくり”が好きで、将来はデザイナーになりたいという思いから、ファッションデザインの専門学校を卒業しました。卒業後はアパレル業界に入り、オンワード樫山で4年間販売職を経験。企画やデザインの仕事を目指して、福岡の中小企業に転職し、そこで服飾雑貨の企画営業を2年間担当しました。アパレル業界での経験は合計6年になります。とは言えこれまでのキャリアを振り返る中で、「ファッションは好きだけれど、仕事としてはもう十分かもしれない」と感じ、新しいことにチャレンジをしたいと思うようになり、転職することを決めました。
──エンジニアを目指したきっかけを教えてください。
次に進む道が決まらないまま退職したものの、“ものづくり”への関心は変わらず、「自分でアプリをつくって起業してみたい」と考えるようになりました。そこで、福岡にあるスタートアップ支援コミュニティ施設に相談し、紹介されたのが起業家養成エンジニア学校「G’s ACADEMY」でした。翌日には願書を提出し、そこからの半年間は毎日フルタイムで学習。アイデアを形にする難しさと、コードを書く楽しさを実感する日々でした。その過程で気づいたのは、自分でゼロから立ち上げようとすると、理想や価値観に偏りすぎてしまい、マネタイズや持続可能性といった事業の現実的な側面まで考えきれず、結果的にボランティアやNPOのようなアイデアに落ち着いてしまっていたということでした。
「0→1で起業するよりも、誰かが持つビジョンやアイデアに共感し、それを一緒に膨らませていく方が、自分にとっては楽しいし得意だ」と感じるようになりました。共感できるビジョンを持つ誰かとともにプロダクトを育てていく。そうした関わり方のほうが、自分の性格や価値観に合っていると実感し、エンジニアとしての道を志すようになったのです。
卒業後はG’s ACADEMYのメンターであり、株式会社tsumugのエンジニアとしても活躍されていた方からお声がけいただき、同社に参画しました。同時に2019年にフリーランスとして独立しました。tsumugではフロントエンドエンジニアとスクラムマスターを兼任し、裁量ある働き方を経験しました。ここで出会ったのが、現クロステック・マネジメント代表の小笠原です。
「一緒に仕事がしたい」信頼が紡ぐ、教育DXへの挑戦

──クロステック・マネジメントに参画することを決めた理由は何だったのでしょうか?
一番大きかったのは、やはり小笠原さんの存在です。tsumug時代に同じチームで長く仕事をしてきて、「この人と一緒にやるのは本当に面白い」と何度も感じていました。思考のスピードや視座の高さに刺激を受ける場面が多く、自然と小笠原さんを信頼し、尊敬する気持ちが芽生えていったのだと思います。そんな小笠原から「こういうことをやろうと思っている」と声をかけてもらったとき、正直、内容はすぐには理解できなかった部分もありました。でも何より、「また一緒に仕事ができる」ということが、とても嬉しかったんです。これまでの関係性のなかで積み重ねてきた信頼と、小笠原さんが描く未来への共感が、クロステック・マネジメントへの参加を決めた一番の理由でした。
また、クロステック・マネジメントが取り組もうとしている「教育に関わるDX」に対してどこか縁のようなものを感じたんです。自分自身、家族や親戚に教員が多く、現場の大変さを近くで見てきたので、自分が教職の道に進んだわけではないけれど、身近な人が苦労していた教育現場を、テクノロジーの力で少しでも変えていけるかもしれない、そんな想いもモチベーションになりました。
仕組み×信頼で進化するチームづくり

──現在はどんな業務を担当していますか?
現在は、クロステック・マネジメントでVPoP(Vice President of Process)として、開発チーム全体のプロセス設計や運用、チームビルディングを担っています。もともとはスクラムマスターとして開発チームを見ていましたが、メンバーが急増し、複数の開発チームが並行して動くようになったことで、組織全体としての体制整備が求められるフェーズに移行しました。そこでDevOps部門が立ち上がり、私はその中で主に“開発プロセス”の設計と運用に責任を持っています。
スクラム開発を前提に、プロダクトオーナー・開発者・スクラムマスターという三つのロールがスムーズに連携できるよう、ツール選定やチーム編成、会議体の再設計など、仕組みそのものを設計・運用する役割です。特定の業務に縛られず、「今、チームが困っていることは何か」「どうすればより快適に成果を出せるか」を考えながら、時にはメンタル面のケアや、チームメンバー個々の働き方の調整にも踏み込んでいます。
最近は、Bizサイドとも連携しながら、開発組織全体の土台づくりを担う機会が増えてきました。プロセス改善を単なる“運用”で終わらせず、“創造”として捉え、組織全体を次のフェーズに導いていくことが今の自分のミッションだと考えています。
──いいモノづくりをするために心がけていることについて教えてください。
いいモノづくりをするために心がけているのは、メンバー1人ひとりの状態にも目を向けることです。組織が拡大し、物理的な距離や多様な働き方の中で孤立感を抱くメンバーもいます。だからこそ、定期的なコミュニケーションを通じて心理的安全性を保ち、悩みやストレスを早期にキャッチアップすることに心がけています。また、コレクティブ型組織の考え方を大切にしています。メンバー全員が互いに支え合い、協力しながらチームとして成果を出していく組織の形を目指しているからです。
人を信じ、人を大切にする。それが結果的に、良いものづくりにつながると信じています。いいチームから、いいプロダクトが生まれる。技術力だけで突き抜けるワンマンな人よりも、関係性の中で力を発揮できる人とチームを作りたい。誰が入っても抜けても、安定してアウトプットが出せる状態が理想です。
挑戦を受け継ぎ、次へつなげる恩送り
──クロステック・マネジメントで働く魅力を教えてください。
クロステック・マネジメントの最大の魅力は、「どう働くかを自分で考えられる余地」が大きいことです。形式的な上下関係や命令ではなく、信頼をベースにした対等な関係の中で、プロとしての裁量を持って働ける。そして、チームの一員としてしっかり見てもらえる安心感があります。個人事業主という立場でありながらも、責任と権限を与えられ、自分で考えチャレンジできる環境が整っています。
評価の軸も成果だけにとどまらず、すぐに結果が出ない難易度の高いプロジェクトにおいても、「チャレンジしたか」「学びがあったか」「チームにとって意味のある時間だったか」といったプロセスが重視されます。だからこそ、「難しいけどやってみよう」と前向きに取り組むことができるのだと思います。
このような信頼と挑戦の文化が根付いているからこそ、個々の力が自然と引き出され、チームとしての大きな力につながっているのだと感じます。